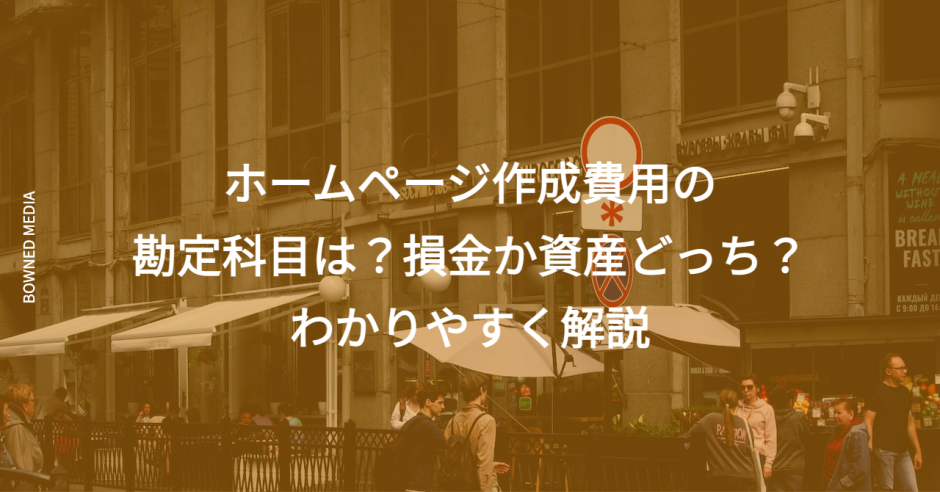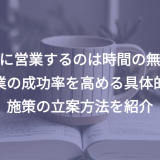※本サイトは一部アフィリエイト広告を利用しています。
使わない日はないほど、日常に浸透したインターネット。ビジネスを始めるにあたって、ホームページの作成を依頼する企業や事業者の方も多いでしょう。
ホームページ作成時にはほとんど意識することのない「勘定科目」ですが、会計処理の際に「ホームページの作成費用の勘定科目って?どのように会計処理すればいい?」と頭を悩ませている方も少なくないようです。
また、気になるのが「ホームページ作成費用は損金扱いになるの?」という点でしょう。結論としては、ケースバイケースで会計処理が変わってきます。
この記事では、ホームページ作成費用の勘定科目について詳しく解説していきます。

目次
ホームページ作成費用は損金?資産?

法人や個人事業主が収入を得るための支出は必要経費として計上することで控除できますが、すべての経費が「損金」として算入できるわけではありません。
損金算入できるかどうかで税金が変わってくるため、勘定科目が気になる方も多いでしょう。
- 「広告宣伝費」の場合……全額を損金算入できる
- 「無形固定資産」の場合……取得金額の一部のみ損金算入
ホームページ作成費用の場合、仕訳によって上記のような違いがあります。ではなぜ、会計処理がケースバイケースで異なるのかというと、技術の進化に伴ってホームページの機能や使い道が多様化しているためであるとされています。
高機能なホームページは単に商品やサービスのPRのみを目的としたものとはいえず、「広告宣伝費」とするのは適切ではありません。そこで、ホームページの用途や機能などによって、会計処理を変える必要が生じているのです。
特例に該当し30万円以下の場合は損金算入可能
なお、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用対象となる中小企業者等の場合、30万円以下であれば内容や機能に関係なく損金算入が可能です。
この特例における取得期間は平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間となります。
ホームページ作成費用の勘定科目は3パターン

自社ホームページの作成を依頼した際にかかる費用の勘定科目は以下の3パターンあります。
- 基本的には「広告宣伝費」
- 1年以上更新しない場合は「繰延資産」または「長期前払費用」
- ソフトウェア機能がある場合は「無形固定資産(資産計上)」
ここから、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1. 基本的には「広告宣伝費」
ホームページ作成費用は、基本的には「広告宣伝費」の勘定科目に仕訳、損金として会計処理を行います。一般的に、ホームページはPRを目的として作成されると考えられるためです。
たとえば、以下のようなホームページ作成費用は勘定科目を広告宣伝費として会計処理できるでしょう。
- コーポレートサイト
- 自社商品・サービス・ビジネスのPRや宣伝を目的としたホームページ
ただし、広告宣伝費とするには「1年以内に更新すること」が前提です。ニュースやお知らせ、コンテンツ追加、デザイン変更などの更新が必要になります。ホームページを広告宣伝費として処理したい場合は、1年に1回でもいいので更新を行いましょう。
2. 1年以上更新しない場合は「繰延資産」または「長期前払費用」
1年以上ホームページを全く更新しない場合は、「繰延資産」または「長期前払費用」として会計処理を行います。
繰延資産とは「すでに支払済みの支出のうち、年度をまたいだ損金処理が認められたもの」のことで、長期前払費用は「貸借対照表の資産の部に計上され、翌期以降に損金処理するもの」です。
繰延資産として会計処理する場合、使用期間に応じて均等償却していきます。
3. ソフトウェア機能がある場合は「無形固定資産(資産計上)」
ソフトウェア機能のような高度な機能が搭載されているホームページの場合、広告宣伝費や繰延資産、長期前払費用ではなく「無形固定資産」として会計処理する必要があります。
ソフトウェア機能と判断されるのは、主に以下のような機能です。
- 会員登録機能、ログイン機能
- オンラインショッピング機能(ショッピングカート機能、クレジットカードなど入金処理機能など)
- サイト内検索機能
- 予約システム・会員システム
- ゲーム機能 など
わかりやすいのが、インターネットでの商品・サービス販売を目的としたホームページであるECサイトです。ECサイトのようなソフトウェア機能を搭載した高機能なホームページは無形固定資産として資産計上し、5年間で均等に減価償却が可能です。
なお、20万円未満のソフトウェアは一括償却資産として処理できます。
ホームページ作成費用は分割して会計処理も可能
ホームページ作成において「広告宣伝費」と「ソフトウェア部分」が明確に区別できる場合、分割して会計処理が可能です。
この場合、広告宣伝費は費用として損金処理、ソフトウェア部分は資産計上し、償却処理を行います。
一方で、「ホームページ作成費用一式」のように明確に分割できない場合は、全額をソフトウェアとして無形固定資産に計上する必要があります。分割できるかできないかは、見積書や請求書の内容によって変わってくるため、事前に確認しておきましょう。
ホームページ運用関連のその他の費用の勘定科目

ホームページは作成後、継続して運用し維持・更新を行っていく必要があります。ここからは、ホームページ運用に関連する費用の勘定科目について解説します。
ドメイン取得費の勘定科目
ホームページ作成時に欠かせないドメインとは、インターネット上の住所のようなものです。「.com」「.co.jp」などが該当し、ホームページを閲覧可能な状態にするために必要です。
ドメイン費用は以下の3つの勘定科目が使われます。
- 通信費
- 広告宣伝費
- 支払手数料
3つの勘定科目の中では「通信費」として損金算入するのが一般的です。
なお、すでに加入済みのプロパイダーなどから、ドメインを取得できる場合があります。そのうえ、無料で提供されることも多く、コストをおさえたい企業としては魅力的に感じますが、あまりおすすめできません。
プロパイダーなどから提供されるドメインは、文字並びが分かりにくいものが多く、企業のホームページとしては適していません。特別な事情ない限りは、ドメインの専門業者から購入したうえで活用することを推奨します。
サーバー費用の勘定科目
サーバーとはホームページ上のデータやプログラムを保存するコンピューターのことで、ホームページの場合はレンタルサーバーやホスティングサービスが使われることが一般的です。
サーバーを維持するためのサーバー費用は以下の3つの勘定科目が使われます。
- 通信費
- 広告宣伝費
- 支払手数料
どの勘定科目を選ぶかは明確なルールがないものの、サーバー費用も「通信費」として計上されることが多いです。ただ、他の支出と勘定科目を分けたいときには、通信費以外を選んでも問題はありませんが、以降も一貫して同じ勘定科目で計上する必要があります。
SSL証明書取得費用の勘定科目
SSLとは、悪意ある第三者からインターネット利用者の個人情報を守るため通信を暗号化する仕組みのことです。
無料で利用できるケースもありますが、サポートの問題や悪用のリスクなどから、有料のSSLを利用するケースも少なくありません。
SSL化に必要なSSL証明書の取得費用は以下の3つの勘定科目で損金算入します。
- 通信費
- 広告宣伝費
- 支払手数料
ただし、中には年間40万円以上など高額なSSL証明書も存在し、この場合はソフトウェアとして資産計上して減価償却の会計処理が必要です。
コンテンツ制作費の勘定科目
外部の会社にコンテンツ制作を依頼した場合、コンテンツ制作費がかかります。
コラム記事やブログ記事の新規追加、修正やリライトなどの場合は「広告宣伝費」の勘定科目で損金算入します。
ただし、追加するコンテンツが「ログイン機能」「オンラインショッピング機能」など高度なソフトウェア機能である場合、広告宣伝費ではなく「無形固定資産」となる場合もあります。
SEO費用の勘定科目
自社ホームページをGoogleなどの検索エンジンで上位表示させたい場合の対策が、SEO(検索エンジン最適化)です。
SEOは広告宣伝とみなされるため、外部SEO会社に依頼した場合の費用は一般的に「広告宣伝費」の勘定科目で損金算入します。ただし、SEO分析ツールなどを導入する場合は「ソフトウェア」として会計処理を行う必要があるケースもあります。
WordPressなどのCMSを用いたホームページの勘定科目
ソフトウェア機能がある場合は「無形固定資産(資産計上)」として会計処理をする必要がありますが、WordPressなどのCMS(コンテンツマネジメントシステム)を利用しているホームページの場合は「無形固定資産(資産計上)」として処理する必要があるのでしょうか?
結論からいうと、CMSを利用したホームページは「広告宣伝費」として会計処理するケースがほとんどのようです。
CMS自体はソフトウェアですが、ホームページを更新することを目的としたソフトウェアであり、1年のうちに頻繁に更新することを前提としています。このため「広告宣伝費」として会計処理するようです。
CMSを用いていても、もしECサイトや会員制機能など大掛かりなシステムが搭載されている場合は「無形固定資産(資産計上)」として会計処理する必要があります。
ホームページ作成時に使える補助金
ホームページ作成時は、補助金を活用することもできます。ホームページ作成時に使える補助金としては、主に以下の3つがあります。適切な会計処理による節税と合わせて、補助金などの制度の活用で負担を軽減しましょう。
- 小規模事業者持続化補助金(日本商工会議所)
- IT導入補助金(経済産業省)
- 地方自治体による独自の補助や助成(各自治体)
それぞれ、どのような補助金なのか、どのような要件で活用できるのか、などについて解説します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、日本商工会議所から支援を受けられる補助金制度です。
最大補助率は3分の2であり、最大補助額は200万円と大規模なホームページ作成で利用しやすい補助金と言えます。ただし、小規模事業者持続化補助金は、公募で申請可否が決まるため要注意です。公募回数は1年に1回程度なので、仮に申し込み期間が過ぎていた場合は、翌年の公募に応募する必要があります。
また、対象となる企業は「数人から十数人」程度の規模の小規模な営利団体となります。そのため、企業規模によっては対象外となるため注意しましょう。他にも、「医療法人」「学校法人」「宗教法人」「福祉法人」などは補助の対象外です。
公募の期間に左右されやすい補助金であるため、小規模事業者持続化補助金の利用を検討している方は、早めに公募の期間を調査し、計画を立てることが重要です。
https://r3.jizokukahojokin.info/
IT導入補助金
IT導入補助金とは、経済産業省による補助金制度の一つです。最大補助率は最大で50%までであり、最大補助額は450万円にもおよびます。他の補助金と比べて、最も高額な支援が受けられる点が特徴です。
IT導入補助金では、通常のホームページの他にも業務システムや会計システムなど、業務に関わるITツールの導入も支援しています。小規模事業者持続化補助金と比べると、要件はそこまで細かくないものの、対象となる業種や企業規模には上限があります。
また、資本金額にも上限が設けられているため、規模の大きい企業は注意が必要です。なお、IT導入補助金の対象業種や規模は以下の通りです。
【業種/資本金/従業員数】
- 製造業・運輸業・建設業/3億円/300人
- ゴム製品製造業/3億円/900人
- ソフトウェア業/3億円/300人
- 卸売業/1億円/100人
- サービス業/5000万円/100人
- 小売業/5000万円/50人
- 旅館業/5000万円/200万円
- 医療法人・社会福祉法人・学校法人/資本金なし/300人
上記の業種、及び資本金や従業員数の上限を確認したうえで、IT導入補助金を考えてみましょう。
なお、IT導入補助金も、小規模事業者持続化補助金同様に申し込み期間が定められています。公募は1年に1回程度となるため、スケジュールと申し込み期間を照らし合せて助成金の利用を検討してください。
地方自治体による独自の補助や助成
上記2つの助成金とは別に、地方自治体が独自に提供している補助や助成が存在します。とはいえ、すべての地方自治体が補助や助成を提供しているわけではないため、まずは市区町村のホームページや公式サイトを確認し、利用できる補助・助成がないかを見てみましょう。
とはいえ、上記2つの助成金と比べると、支援される金額は少ないことが多いです。自社にとって十分な支援となるのかは、地方自治体によって異なります。また、地方自治体の補助・助成と、上記2つの助成金を併用することはできません。
上記2つのうちのいずれかの助成金を利用できそうであれば、地方自治体の補助・助成金は一旦断念し、別の機会に利用することをおすすめします。
なお、ホームページは無料で作成することも可能です。以下の記事ではおすすめのホームページ無料作成サービスをご紹介しておりますのでこちらもぜひチェックしてみてください。
【2025年最新】ホームページ無料作成サービス14選!メリットとデメリットを比較
補助金でホームページ作成・更新代行サービスも利用できます
Bownedを運営する株式会社ヴァルワークスでは、中小企業・小規模事業者さま向けにサブスクリプション型のホームページ作成サービス「NOTEMA(ノーテマ)」をご提供しています。
「ホームページを作って終わりではなく、作ったあともお客様をサポートしていきたい」そんな思いでこのサービスをつくりました。
今お持ちのURL(ドメイン)を変えることなく、SEOやユーザビリティなどのポイントをおさえたスタイリッシュなホームページを作成できます。安心の定額制なので保守・運用・更新もすべておまかせください。御社事業をしっかりとヒアリングしたうえで、サイトの構成やデザインをご提案します。
まとめ
ホームページ作成費用の勘定科目は、ケースバイケースによって異なりますが、基本的には「広告宣伝費」に該当します。ただし、1年以上更新しないことが前提の場合、「繰延資産」もしくは「長期前払費用」となります。
ソフトウェア機能を有したホームページの場合は「無形固定資産」となり、ホームページの特徴や機能によっても勘定科目・処理方法が変わってくるため、しっかり確認した上で処理を行いましょう。